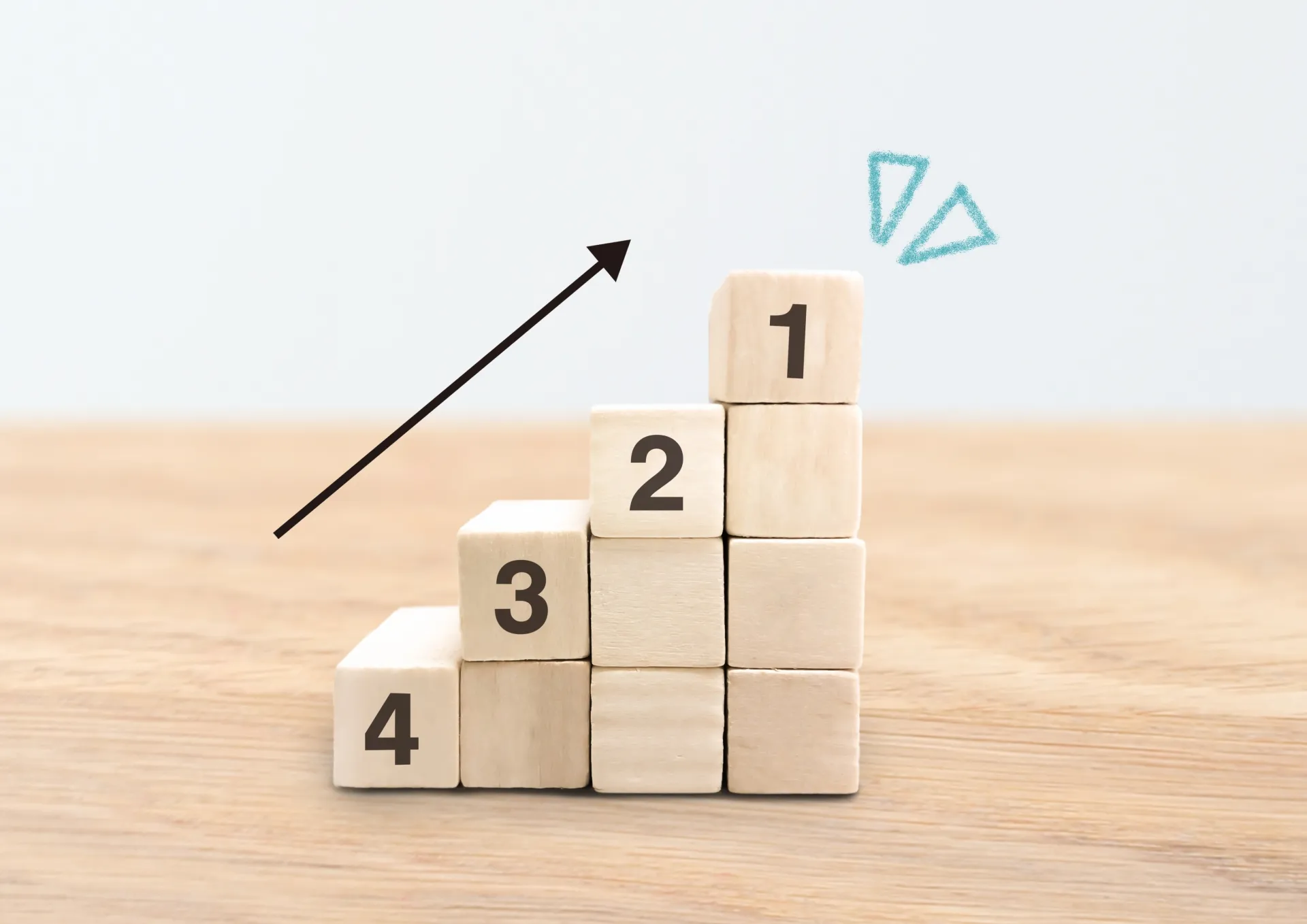「せっかくWebサイトにアクセスしてくれたのに、すぐに離れてしまうユーザーが多い」「直帰率と離脱率、どちらを改善すれば良いのか分からない」
企業のWeb担当者様であれば、このような課題に直面することは少なくありません。Webサイトへの集客に成功しても、ユーザーがすぐに離れてしまっては、せっかくの努力が水の泡になってしまいます。特に「離脱率」と「直帰率」という2つの指標は、サイトの改善点を見つける上で非常に重要ですが、その違いや具体的な活用方法について曖昧な認識のまま運用しているケースも見受けられます。
本記事では、自社のコーポレートサイト制作を検討している企業担当者様向けに、離脱率と直帰率の明確な違いから、それぞれの指標が示す意味、そしてこれらのデータを活用してサイトを改善するための具体的な方法を詳しく解説します。ユーザーが「また来たい」と思う魅力的なWebサイトを構築し、企業の信頼感と集客力を高める一助となれば幸いです。
Webサイト分析でなぜ数値を見る必要があるのか
離脱率と直帰率について深く理解する前に、まずWebサイト分析においてなぜ「率」という数値が重要なのか、その前提知識を整理しておきましょう。
Webサイトを運用する目的は、企業によって様々ですが、最終的にはビジネス成果に繋がることが求められます。そのためには、サイトを訪れるユーザーがどのような行動をしているのかを客観的に把握し、ボトルネックとなっている箇所を特定して改善していく必要があります。
「率」の指標は、個々のアクセス数やページビュー数といった絶対数だけでは見えてこない、ユーザー行動の傾向やサイトのパフォーマンスを測る上で非常に有効です。例えば、「アクセス数が増えた!」と喜んでいても、直帰率が異常に高ければ、流入経路とコンテンツ内容にミスマッチがあるのかもしれません。逆に、アクセス数が少なくても、コンバージョン率が高ければ、質の高いユーザーを効率的に集客できていると判断できます。
主なWebサイト分析における「率」の指標としては、以下のようなものがあります。
- クリック率(CTR): 広告や検索結果の表示回数に対して、クリックされた割合。
- コンバージョン率(CVR): サイトに訪問したユーザーのうち、目標とする行動(資料請求、問い合わせ、購入など)を達成した割合。
- エンゲージメント率: ユーザーがサイト内で積極的に行動した割合(ページを深く読み込んだ、動画を再生したなど、Google Analytics 4で重視される指標)。
そして、本記事のテーマである「離脱率」と「直帰率」も、ユーザーがサイトから離れる行動を示す重要な「率」の指標です。これらの数値を正しく理解し、分析することで、ユーザーがサイトを離れてしまう原因を特定し、効果的な改善策を講じることが可能になります。
Webサイトのパフォーマンスを最大化するためには、これらの「率」を常に意識し、改善サイクルを回していくことが不可欠なのです。
関連記事:ホームページの離脱率は?UX改善で成果を上げるポイント
離脱率と直帰率の決定的な違いとは?
いよいよ本題の、離脱率と直帰率の明確な違いについて解説します。この2つの指標は混同されがちですが、それぞれが示す意味合いは大きく異なります。
1. 直帰率(Bounce Rate)
直帰率とは、サイトに訪問したユーザーが、最初の1ページだけを閲覧して、他のページに移動することなくサイトを離れてしまった割合を指します。
もっと分かりやすく言うと、
- ユーザーがAページにアクセス
- Aページだけを見て、すぐにサイトから出て行ってしまった
この場合が「直帰」となります。最初の1ページしか見なかった(=1セッションにおけるページビューが1だった)セッションの割合、と考えると良いでしょう。
計算式:
直帰数 ÷ セッション数 × 100
直帰率が高い場合の原因と対策の方向性:
直帰率が高いということは、ユーザーがサイトの最初のページに何らかの不満を感じ、それ以上サイト内を回遊するモチベーションを失ってしまった可能性が高いと言えます。
- 原因1:検索意図とのミスマッチ
- ユーザーが検索したキーワードと、ランディングページの内容が合っていない。
- 広告から流入した場合、広告文とページ内容に乖離がある。
- 対策: ターゲットキーワードの見直し、コンテンツ内容の改善、広告文とランディングページの一貫性確保。
- 原因2:ページの品質・情報不足
- コンテンツが薄い、情報が古い、誤字脱字が多いなど、信頼性に欠ける。
- ユーザーが求めている情報が見つからない。
- 対策: 網羅的で質の高いコンテンツ作成、情報の定期的な更新、ユーザーニーズを深掘りした情報提供。
- 原因3:ユーザーインターフェース(UI)/ユーザーエクスペリエンス(UX)の問題
- デザインが見にくい、文字が読みにくい。
- ナビゲーションが分かりにくい、次の行動への導線がない。
- ページの表示速度が遅い。
- モバイル対応が不十分。
- 対策: レイアウトの改善、文字サイズや行間の調整、明確なCTA(Call To Action)設置、ページ表示速度の改善、レスポンシブデザインの導入。
直帰率は、主にランディングページの品質や、流入経路との整合性に問題がないかを判断する重要な指標です。
2. 離脱率(Exit Rate)
離脱率とは、特定のページからユーザーがサイトを離れてしまった割合を指します。
もっと分かりやすく言うと、
- ユーザーがサイト内の複数のページ(例:A→B→C)を閲覧した後、
- Cページを見て、サイトから出て行ってしまった
この場合、Cページの「離脱」とカウントされます。ユーザーがサイト内でどこを回遊したかは関係なく、そのページを「最後に閲覧してサイトを去った」セッションの割合、と考えると良いでしょう。
計算式:
特定のページからの離脱数 ÷ そのページのページビュー数 × 100
離脱率が高い場合の原因と対策の方向性:
離脱率が高いということは、そのページがユーザーのサイト回遊を止めてしまう要因になっている可能性が高いと言えます。ただし、そのページの役割によって、離脱率の解釈は大きく変わります。
- 原因1:ユーザーの目的達成(良い離脱)
- 「お問い合わせ完了ページ」「資料ダウンロード完了ページ」など、ユーザーが目的を達成した結果として離脱するページ。
- 対策: この場合は特に改善の必要はありませんが、サンクスページ内に次の行動を促すリンク(関連ページへの誘導、SNSフォローなど)を設置することで、エンゲージメントを高めることも可能です。
- 原因2:コンテンツの終着点としての役割(許容される離脱)
- ブログ記事の最後、企業情報の最終ページなど、ユーザーが求める情報がそこで完結している場合。
- 対策: 関連コンテンツへの誘導、CTAの設置、コメント欄の設置などにより、回遊を促す工夫は有効です。
- 原因3:コンテンツの不満(悪い離脱)
- ユーザーが期待する情報が得られなかった、次のアクションが不明瞭だった。
- 情報が古かったり、閲覧しにくかったりする。
- 対策: コンテンツの質向上、関連コンテンツへの内部リンク強化、CTAの最適化、ユーザーの次に知りたいであろう情報への誘導。
- 原因4:技術的な問題
- エラーページ、表示崩れ、ページの読み込みが極端に遅い。
- 対策: エラーの修正、表示の最適化、表示速度の改善。
離脱率は、特定のページがユーザーの回遊を阻害しているか、あるいはそのページの役割を適切に果たしているかを判断する指標です。
まとめると
| 指標 | 意味合い | 特徴 | 改善の焦点 |
| 直帰率 | サイトに最初に訪れたページで、他のページに移動せずに離れた割合。 | 1ページしか見なかったセッションの割合。 | ランディングページの質、流入経路との整合性。 |
| 離脱率 | 特定のページを最後に閲覧して、サイトから離れてしまった割合。 | サイト内のどこからでも発生しうる。そのページが「サイトの出口」となる割合。 | 各ページのコンテンツ、次の行動への誘導、ページの役割。 |
このように、直帰率は「入り口」の課題を、離脱率は「出口」の課題をそれぞれ示していると理解すると分かりやすいでしょう。
離脱率と直帰率のデータをサイト改善に活かす具体的な方法
離脱率と直帰率の違いを理解した上で、いよいよこれらのデータをWebサイトの改善にどのように活かすか、具体的な方法を解説します。これらの指標は、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールで確認することができます。
1. 高い直帰率の改善アプローチ
高い直帰率は、サイトの入り口に問題があることを示唆しています。改善の第一歩は、どの流入経路からどのページで直帰率が高いのかを特定することです。
ステップ1:直帰率の高いランディングページを特定する
Google Analyticsの「行動」>「サイトコンテンツ」>「ランディングページ」レポートで、直帰率の高いページを見つけ出しましょう。特に、検索流入が多いページや、広告からの流入があるページで直帰率が高い場合は、優先的に改善が必要です。
ステップ2:流入キーワード・経路とコンテンツのミスマッチを解消する
Google Search Consoleで、そのランディングページに流入している検索キーワードを確認します。
- 「ユーザーがどのような意図でそのキーワードを検索したのか?」
- 「ランディングページの内容は、その検索意図を十分に満たしているか?」
この2点を徹底的に検証します。もしキーワードとコンテンツに乖離がある場合は、以下の対策を検討します。 - コンテンツ内容の加筆・修正: ユーザーの検索意図に沿った情報を追加したり、分かりやすく改善したりします。
- キーワードの再選定: そもそもそのキーワードで上位表示を目指すべきではないと判断した場合、別のキーワードでコンテンツを作成することも視野に入れます。
- 広告文の調整: 広告から直帰率が高い場合は、広告文とランディングページの内容が一致しているか確認し、必要に応じて広告文を修正します。
ステップ3:ランディングページのUI/UXを改善する
- ファーストビューの改善: ページを開いた瞬間にユーザーの心を掴めるか。タイトル、導入文、画像、CTAなどが分かりやすく魅力的かを確認します。
- 読みやすさの向上: 文字サイズ、行間、配色、見出しの分かりやすさなどを改善します。箇条書きや図解なども効果的です。
- 信頼性の確保: 誤字脱字、情報の正確性、最新性を確認します。企業サイトであれば、専門性や権威性を示す要素(実績、導入事例など)を適切に配置することも重要です。
- 明確なCTAの設置: ユーザーに次に何をしてほしいのか(資料請求、お問い合わせ、関連記事を読むなど)を明確に示し、ボタンデザインや配置を最適化します。
- ページ表示速度の高速化: 画像の圧縮、サーバーの最適化などを行い、ページの読み込み時間を短縮します。
- モバイル対応の徹底: スマートフォンからのアクセスでも、ストレスなく閲覧・操作できるかを確認します。
2. 高い離脱率の改善アプローチ
離脱率の改善は、まず「そのページからの離脱が望ましいものか、望ましくないものか」を判断することから始まります。
ステップ1:離脱率の高いページを特定し、そのページの役割を再確認する
Google Analyticsの「行動」>「サイトコンテンツ」>「すべてのページ」レポートで、離脱率の高いページを見つけます。
その上で、そのページがWebサイト内でどのような役割を果たしているのかを検討します。
- **「お問い合わせ完了ページ」や「資料ダウンロード完了ページ」**のように、ユーザーが目的を達成してサイトを去るページであれば、離脱率が高くても問題ありません。むしろ、目標達成を示す良いサインです。
- ブログ記事やサービス紹介ページなど、次の行動に繋げたいページで離脱率が高い場合は、改善が必要です。
ステップ2:ユーザーの次の行動への導線を強化する
望ましくない離脱が発生しているページでは、ユーザーが次に何を知りたいか、何をすべきかを明確にし、適切な導線を設置します。
- 関連コンテンツへの内部リンク: 記事の末尾や途中に、関連性の高い他の記事やサービスページへのリンクを設置します。
- CTA(Call To Action)の最適化: 記事の内容に関連する資料請求、お問い合わせ、メルマガ登録などのCTAを、ユーザーの目に留まりやすい位置に配置します。デザインも工夫し、クリックしたくなるような魅力を与えましょう。
- サイト内検索の視認性向上: ユーザーが求めている情報に辿り着きやすいよう、サイト内検索窓の配置を見直します。
- 人気記事・おすすめ記事の表示: サイドバーやフッターに、人気の記事や企業が読ませたい記事を掲載し、回遊を促します。
ステップ3:コンテンツ内容とユーザーの期待を一致させる
そのページで伝えたい情報が、ユーザーに十分に伝わっているかを確認します。
- 情報の網羅性と深さ: ユーザーが抱くであろう疑問がすべて解消されているか。
- 分かりやすい表現: 専門用語ばかりになっていないか、図解や動画などを活用して視覚的に分かりやすく工夫できないか。
- 最新性の維持: 情報が古くなっていないか、定期的に更新します。
ステップ4:技術的な問題やUXの障害を取り除く
表示エラーが頻発するページや、レイアウトが崩れているページ、表示速度が極端に遅いページは、ユーザーの離脱を招きます。CMSの更新、画像の最適化、エラーの修正など、技術的な改善も定期的に行いましょう。
3. 離脱率・直帰率の目標設定とベンチマーク
一般的に、直帰率や離脱率の「良い数値」は、サイトの種類や業種、コンテンツの内容によって大きく異なります。
- ブログ記事: 比較的直帰率が高くなる傾向にあります(50~80%)。
- ECサイトのカテゴリページ: 回遊が期待されるため、直帰率は低めが望ましい(20~40%)。
- お問い合わせページ(最終ページ): 離脱率が高くても問題ない。
そのため、明確な目標値を設定する際は、業界平均や競合サイトのデータ、そして自社サイトの過去の推移を参考にしましょう。最も重要なのは、**「改善前の自社サイトの数値よりも良くなったか」**という視点です。
例えば、「直帰率の高い上位5ページについて、次回の月次レポートまでに直帰率を5%改善する」といった具体的な目標を設定し、PDCAサイクルを回していくことが重要です。
Google Analytics 4での指標の捉え方
近年、Google Analyticsのバージョンが「ユニバーサルアナリティクス(UA)」から「Google Analytics 4(GA4)」に移行しました。GA4では、ユーザー行動の計測方法がイベントベースに変更され、一部の指標の捉え方や名称も変わっています。
GA4における離脱率と直帰率についても、UAとは少し異なる点がありますので、補足として解説します。
GA4の「エンゲージメント」と「直帰率」
GA4では、UAでいう「直帰」の反対の概念として「エンゲージメント(Engaged Session)」という指標を重視しています。
エンゲージメントセッションの定義:
以下のいずれかを満たすセッションを「エンゲージメントセッション」と定義します。
- 10秒を超えて継続したセッション
- コンバージョンイベントが発生したセッション
- 2回以上のページビューまたはスクリーンビューが発生したセッション
GA4の直帰率:
GA4における直帰率は、「エンゲージメントセッションではなかったセッションの割合」として定義されます。
つまり、エンゲージメント率の逆数がGA4の直帰率に近い概念となります。
UAとGA4の直帰率の違い:
- UAの直帰率: 1ページだけ見て離脱したセッションの割合
- GA4の直帰率: 10秒未満で離脱し、コンバージョンもなく、1ページしか見なかったセッションの割合
このように、GA4の直帰率はUAよりも定義が厳しくなっています。例えば、あるページにアクセスし、じっくり20秒間読んだ後に離脱した場合、UAでは直帰とカウントされますが、GA4では「10秒を超えて継続」しているため、直帰とはカウントされず、エンゲージメントセッションとなります。
この違いにより、一般的にGA4の直帰率はUAの直帰率よりも低い数値になる傾向があります。
GA4の「離脱率」
GA4でも「離脱率」という指標は存在しますが、UAほど前面に出てくる指標ではありません。ページレポートなどで確認することが可能です。基本的な意味合いはUAの離脱率と同様で、「そのページからサイトを離れた割合」を示します。
GA4で重視される「エンゲージメント率」
GA4では、直帰率よりも「エンゲージメント率」を積極的に見ることで、ユーザーがサイト内でどの程度積極的に行動しているかを把握することが推奨されます。エンゲージメント率が高いほど、ユーザーはサイトコンテンツに関心を持ち、有益な体験をしていると判断できます。
したがって、GA4に移行済みの企業担当者様は、直帰率だけでなく、エンゲージメント率も合わせて確認し、ユーザーの行動を多角的に分析することが重要です。高いエンゲージメント率を目指すことで、結果的に直帰率や離脱率の改善にも繋がるでしょう。
まとめ:離脱率と直帰率を理解しユーザーが「帰りたくない」サイトへ
本記事では、Webサイトの改善に不可欠な「離脱率」と「直帰率」について、その明確な違いから具体的な分析方法、改善策までを詳しく解説しました。
- 直帰率は、ユーザーがサイトに最初に訪れたページで、他のページに移動せずに離れてしまった割合です。ランディングページの品質や、流入経路とのミスマッチが主な原因となります。
- 離脱率は、特定のページを最後に閲覧してサイトから離れてしまった割合です。そのページの役割によって解釈が異なり、ユーザーの次の行動への導線やコンテンツの質が改善のポイントとなります。
- GA4では「エンゲージメント率」も重要な指標として加わり、ユーザーの積極的な行動を測る指標となっています。
これらの指標は、単なる数値ではなく、サイトを訪れたユーザーの「心の声」を表しています。「なぜこのページで離れてしまったのか?」「どうすればもっとサイト内を回遊してくれるのか?」というユーザー視点に立ち返り、仮説と検証を繰り返すことが、サイト改善の成功に繋がります。
貴社のコーポレートサイトが、ユーザーにとって価値ある情報を提供し、期待に応える「居心地の良い場所」となるよう、本記事でご紹介した分析と改善のポイントをぜひお役立てください。離脱率や直帰率を意識したサイト構築を通じて、企業の信頼感を高め、確かな集客力を手に入れましょう。