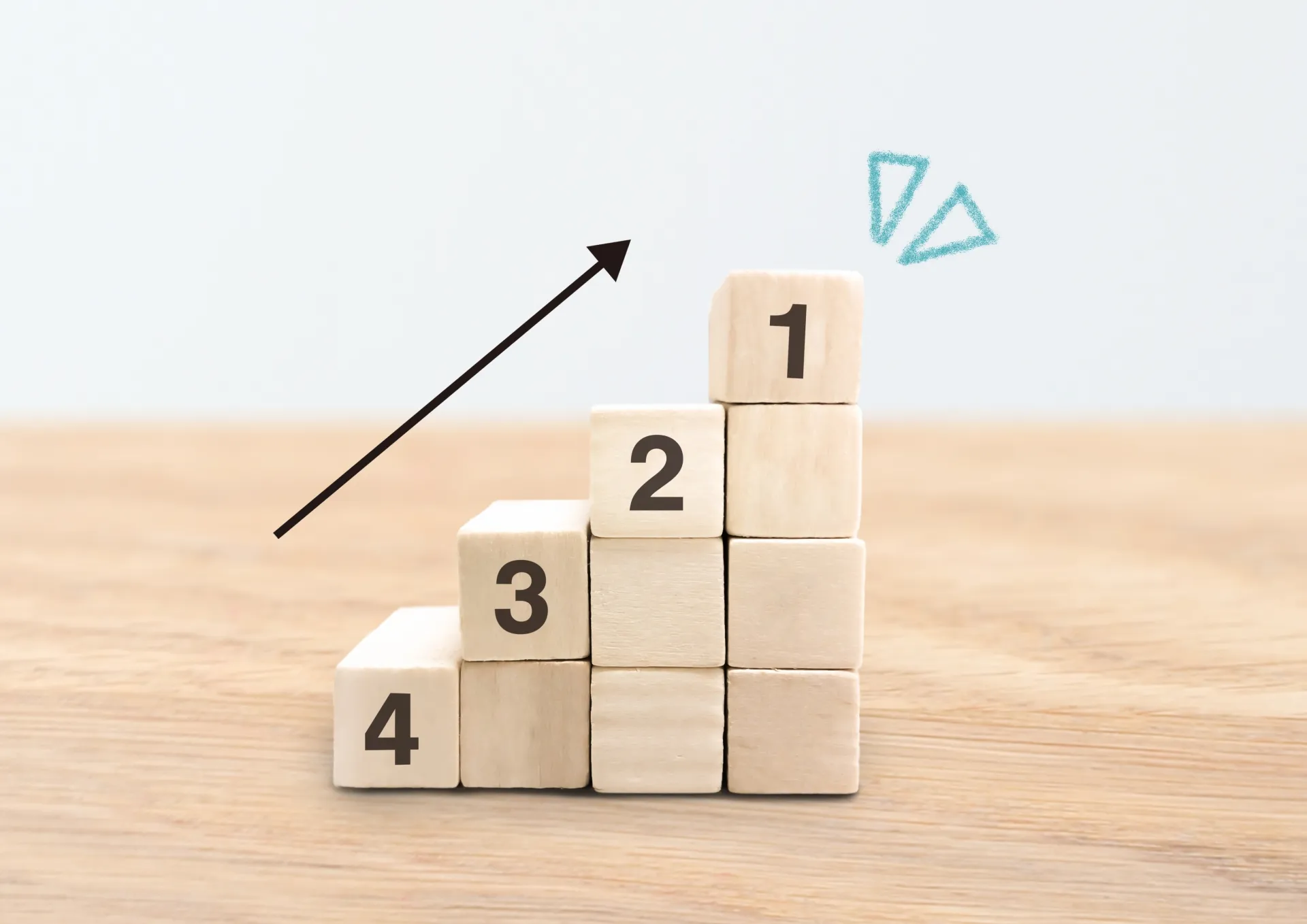「自社のホームページをリニューアルしたいけれど、どのようなデザインにすれば良いか迷っている」
「競合他社との差別化を図り、ブランドイメージをしっかり伝えたいが、漠然としたイメージしか湧かない」
企業のホームページ担当者様であれば、このようなお悩みを抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。ホームページは企業の「顔」であり、そのデザインは訪問者に与える第一印象を大きく左右します。しかし、単に「おしゃれなデザイン」や「流行のデザイン」を追い求めるだけでは、企業の目標達成に繋がる効果的なサイトにはなりません。
ここで重要になるのが、「デザインコンセプト」です。明確なデザインコンセプトがなければ、制作プロセスで方向性を見失ったり、結果的に企業らしさが伝わらない一貫性のないデザインになってしまったりするリスクがあります。
本記事では、コーポレートサイトの制作やリニューアルを検討している企業担当者様に向けて、ホームページの成功に不可欠なデザインコンセプトの重要性から、その具体的な決め方、そして実践手順までを分かりやすく解説します。明確なコンセプトを設定し、企業の信頼感と集客力を高めるサイト作りを実現しましょう。
デザインコンセプトとは?目的達成のための羅針盤
デザインコンセプトの具体的な決め方を学ぶ前に、まず「デザインコンセプトとは何か」という前提知識をしっかりと理解しておきましょう。
デザインコンセプトの定義
デザインコンセプトとは、**「Webサイト(またはデザイン対象全般)を通じて、誰に、何を伝え、どのような感情を抱かせ、最終的にどのような行動を促したいのか」**を言語化した「デザインの核となる考え方」や「中心となる思想」のことです。これは単なる「おしゃれ」「かっこいい」といった抽象的なイメージではなく、具体的な目的やターゲットに基づいて構築されるものです。
例えるならば、建物を建てる際の「設計思想」や、新製品を開発する際の「開発コンセプト」に相当します。このコンセプトが明確であればあるほど、デザインの方向性が定まり、制作プロセス全体がスムーズに進みます。
デザインコンセプトが重要な理由
なぜ、ホームページ制作においてデザインコンセプトがそこまで重要なのでしょうか。
- 一貫性のあるブランドイメージ構築:
コンセプトが明確であれば、サイト全体の色使い、フォント、写真、イラスト、レイアウトといった全てのデザイン要素に一貫性が生まれます。これにより、訪問者に対して企業のブランドイメージをブレなく伝えることができます。 - ターゲットユーザーへの的確な訴求:
誰に何を伝えたいのかが明確になるため、ターゲットユーザーの共感を呼び、行動を促すデザインが可能になります。ターゲットが求める情報や体験を提供しやすくなります。 - 制作チーム内の共通認識:
コンセプトは、ディレクター、デザイナー、エンジニアといった制作に携わるメンバー全員が共有すべき指針となります。これにより、認識のズレを防ぎ、効率的なコミュニケーションとスムーズな制作進行が実現します。 - 評価軸の明確化:
デザイン案が出揃った際、コンセプトという評価軸があれば、「このデザインはコンセプトに合致しているか?」「ターゲットに響くか?」といった客観的な視点で判断できます。感覚的な好き嫌いだけで判断するのを防ぎます。 - 目的達成への貢献:
最終的にWebサイトで達成したいビジネス目標(問い合わせ増加、資料請求、ブランディング強化など)に貢献するデザインを構築するための羅針盤となります。単なる見た目の良さだけでなく、成果に繋がるデザインを目指せます。
このように、デザインコンセプトは単なるデザインの指針に留まらず、企業のWeb戦略を成功に導くための不可欠な要素と言えるでしょう。
関連記事:効果的なデザインコンセプトの作り方とは?基本とポイントを解説
成功するホームページのデザインコンセプトの決め方:実践手順
それでは、具体的なデザインコンセプトの決め方について、ステップバイステップで解説していきます。
ステップ1:Webサイトの「目的」を明確にする
デザインコンセプトを考える上で、最も根本となるのが「なぜこのWebサイトを作るのか(リニューアルするのか)」という目的の明確化です。目的が曖昧なままでは、コンセプトもブレてしまいます。
- 事業目標との連携:
Webサイトの目的は、必ず企業の事業目標と連携している必要があります。「売上を〇%向上させる」「新規顧客獲得数を〇件増やす」「採用応募者数を〇倍にする」など、具体的な事業目標とWebサイトがどのように貢献するのかを言語化します。 - Webサイトの具体的な役割:
事業目標を踏まえ、Webサイトが果たすべき具体的な役割を決定します。- 企業の信頼性を高めるブランディングサイト
- 製品・サービスの魅力を伝え、問い合わせを増やす集客サイト
- 採用活動を強化するリクルートサイト
- 既存顧客への情報提供やサポートを行うポータルサイト
これらの役割に応じて、デザインの方向性も大きく変わってきます。
- KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)の設定:
目的を達成するための具体的な指標(例:問い合わせ数、資料請求数、Webサイト経由の売上、セッション数、PV数、滞在時間など)を設定します。これにより、デザインコンセプトがこれらの指標にどう影響するかを意識するようになります。
質問例:
- このWebサイトで最も達成したいことは何か?
- その目的は、具体的な数値でどのように測定できるか?
- Webサイトは、会社のどの事業課題を解決するのか?
ステップ2:ターゲットユーザーを深く理解する
Webサイトの目的が定まったら、次に「誰に」その目的を達成させたいのか、つまりターゲットユーザーを深く理解することが重要です。
- ペルソナ設定:
ターゲットユーザーの性別、年齢、職業、役職、趣味、価値観、Webサイトを訪れる目的、抱えている課題、情報収集の方法など、架空の具体的な人物像(ペルソナ)を設定します。これにより、漠然とした「顧客」が、まるで目の前にいるかのような具体的な存在になり、その人に響くデザインを考案しやすくなります。- ヒアリング: 営業担当者、カスタマーサポート担当者、既存顧客へのアンケートやインタビューなどを通じて、具体的な情報を収集します。
- アクセス解析: 既存サイトがあれば、Google Analyticsなどのツールを使ってユーザーの属性や行動データを分析します。
- ユーザーニーズと行動予測:
設定したペルソナが、Webサイトを訪れた際に何を求め、どのような行動を取るかを予測します。- 知りたい情報は何?
- どのような不安や疑問を抱いている?
- どのようなデザインやコンテンツに親しみを感じる?
- 最終的にどのような行動を起こしてほしい?(問い合わせ、資料請求、購入など)
質問例:
- 当社の製品・サービスを利用する主な顧客はどのような人か?
- 彼らはWebサイトで何を解決したいと考えているか?
- どのような情報や表現方法が彼らの心に響くか?
- 彼らはどのようなデバイス(PC/スマホ)で主にサイトを閲覧するか?
ステップ3:企業の「らしさ」を定義する(ブランドイメージの言語化)
自社のWebサイトである以上、「らしさ」を表現することは非常に重要です。競合他社との差別化を図り、独自の価値を伝えるための要素を明確にします。
- 企業の強み・特徴:
自社の製品・サービスの強み、他社にはない独自性、技術力、企業文化、提供する価値などを言語化します。- 「高品質」「先進的」「親しみやすい」「信頼性」「革新的」「地域密着型」など、キーワードを複数挙げ、そこから核となるものを絞り込みます。
- ブランドアイデンティティの確認:
既にロゴやコーポレートカラー、ブランドガイドラインが存在する場合は、それを尊重し、Webサイトのデザインもそれに沿ったものにします。まだ明確なブランドアイデンティティがない場合は、この機会に検討することも有効です。 - 競合サイトの分析:
競合他社のWebサイトを分析し、どのようなデザインコンセプトで情報を発信しているかを把握します。その上で、自社がどう差別化を図るかを検討します。- 「競合は堅実なイメージなので、当社はもっと先進的な印象を与えたい」
- 「競合は文字情報が多いので、当社はビジュアルで魅力を伝えたい」
質問例:
- 当社の最も大きな強みは何か?
- お客様にどのようなイメージを持ってほしいか?
- 当社の企業文化や哲学をデザインでどう表現したいか?
- 競合サイトと比べて、当社はどのように見られたいか?
ステップ4:キーワードとイメージを抽出・統合しコンセプトを言語化する
目的、ターゲット、企業の「らしさ」が明確になったら、これらを統合し、具体的なデザインコンセプトのキーワードやイメージを抽出していきます。
- 連想されるキーワードの洗い出し:
ステップ1~3で出てきた要素から、デザインに繋がるキーワードを自由に連想し、書き出します。- 例: 「信頼」「先進」「親しみ」「安心」「スピード」「高品質」「専門」「洗練」「シンプル」「ダイナミック」「温かい」「未来志向」など。
- イメージボード(ムードボード)の作成(視覚化):
洗い出したキーワードや目指す雰囲気、ターゲットに響くであろう写真、色、フォント、イラスト、レイアウトの参考例などを集めて、一枚のボード(デジタルでも物理でも可)にまとめます。これは、抽象的なイメージを具体的な視覚情報に落とし込む作業です。- Pinterestなどのツールも活用できます。
- 競合他社だけでなく、異業種のサイトや雑誌、広告などからインスピレーションを得るのも有効です。
- コンセプトステートメントの言語化:
集まったキーワードとイメージを基に、以下の要素を含んだ簡潔な言葉でデザインコンセプトを言語化します。- 誰に (ターゲット): 「〜を求めるターゲットユーザーに」
- 何を伝え (提供価値/メッセージ): 「〜というメッセージを」
- どう感じさせ (感情/印象): 「〜と感じさせ、」
- 最終的にどうしたいか (行動): 「〜という行動を促す」
- どのような表現で (デザイン要素): 「そのために、〜なトーン&マナーで表現する。」
- 「【企業の課題解決を求める担当者】に、【信頼性と専門性の高さ】を、【安心感のあるトーン&マナー】で伝え、【資料請求や問い合わせに繋げる】ための、『信頼と先進性を兼ね備えた、ミニマルで分かりやすいデザイン』」
- 「【IT業界でキャリアアップを目指す若手】に、【革新的な技術と成長できる環境】を、【活気と未来を感じさせるダイナミックなデザイン】で伝え、【採用応募に繋げる】ための、『挑戦と可能性を表現する、モダンで躍動感のあるデザイン』」
このコンセプトステートメントは、制作チーム全員がいつでも立ち返るべき指針となります。
ステップ5:デザイン要素への落とし込み
言語化したデザインコンセプトを、具体的なデザイン要素に落とし込んでいきます。
- キービジュアル・写真:
コンセプトに沿った写真素材やイラストの選定基準を明確にします。(例:「信頼感」なら実直なイメージ、「先進性」なら未来感のあるイメージ) - カラーパレット:
コンセプトを表現するメインカラー、サブカラー、アクセントカラーを決定します。色の持つ心理効果を意識しましょう。(例:「安心感」なら青系、「活気」なら暖色系) - フォント(書体):
和文・欧文フォントを選定します。フォントの種類はサイトの印象を大きく左右します。(例:「信頼性」なら明朝体やゴシック体、「親しみやすさ」なら丸ゴシック体) - レイアウト・グリッドシステム:
情報の優先順位や視線の動きを考慮し、コンセプトに沿ったレイアウトの方向性を決定します。(例:「シンプル」なら余白を多めに、「ダイナミック」なら大胆な配置) - アイコン・イラスト・アニメーション:
サイト全体のトーン&マナーに合致するスタイルを選びます。
これらの要素は、最終的にデザインガイドラインとしてまとめられ、制作全体の指針となります。
デザインコンセプト決定後の一貫性を保つための運用
デザインコンセプトは、決めて終わりではありません。ホームページの運用を通じて、その一貫性を保ち、目的達成に繋げることが重要です。
1. デザインガイドラインの作成と共有
決定したデザインコンセプトと、それに紐づく具体的なデザイン要素(カラーパレット、フォント、写真のトーン、アイコンのスタイル、レイアウトのルールなど)を「デザインガイドライン」として文書化し、制作チームだけでなく、社内の関係者全員で共有しましょう。
これにより、将来的にサイトの更新やコンテンツ追加を行う際も、コンセプトから逸脱することなく、一貫したブランドイメージを保つことができます。
2. コンテンツ制作との連携
デザインコンセプトは、ビジュアルだけでなく、サイトに掲載するコンテンツ(テキスト、動画など)のトーン&マナーにも影響します。
- キャッチコピー: コンセプトに沿った言葉遣いやメッセージング。
- 文章のトーン: 「堅実な表現」「親しみやすい表現」「専門的な表現」など、コンセプトに合ったトーンで記事や説明文を作成します。
- 動画やブログ記事のテーマ: コンセプトに合致するテーマや内容を選定します。
コンテンツとデザインが一体となることで、より強力にメッセージを伝え、ターゲットユーザーに響くホームページとなります。
3. 定期的な見直しと改善
Webサイトを取り巻く環境(市場、競合、ユーザーニーズ、技術)は常に変化します。そのため、一度決めたデザインコンセプトも、定期的に見直し、必要に応じて改善していく視点が重要です。
- アクセス解析データ: GA4などのデータから、ターゲットユーザーが期待通りの行動をしているか、サイトの印象は意図通りに伝わっているかを分析します。
- ユーザーテスト/ヒアリング: 実際のユーザーにサイトを見てもらい、感想や意見を聞くことで、客観的な評価を得られます。
- 市場の変化: 業界のトレンドや競合サイトの動向を定期的にチェックします。
これらのフィードバックを基に、デザインコンセプトそのものや、それに紐づくデザイン要素を柔軟に調整していくことで、常に最適なWebサイトを維持することができます。
まとめ:明確なデザインコンセプトで企業の信頼と成長を築く
ホームページ制作におけるデザインコンセプトの決め方について、その重要性から具体的な手順、そして運用時のポイントまでを解説しました。
デザインコンセプトは、単なる見た目の良さを追求するものではありません。
「誰に、何を伝え、どう感じさせ、最終的にどのような行動を促したいのか」
という明確な目的とターゲットユーザーの理解に基づき、企業の「らしさ」を最大限に引き出すための羅針盤です。
本記事でご紹介した以下のステップを参考に、ぜひ自社のホームページ制作において、明確で効果的なデザインコンセプトを構築してみてください。
- Webサイトの「目的」を明確にする
- ターゲットユーザーを深く理解する
- 企業の「らしさ」を定義する(ブランドイメージの言語化)
- キーワードとイメージを抽出・統合しコンセプトを言語化する
- デザイン要素への落とし込み
明確なデザインコンセプトは、企業担当者様と制作チームが共通認識を持ち、一貫性のあるブランドイメージを構築し、最終的には企業の信頼感と集客力を高める強力な武器となります。時間をかけてしっかりとコンセプトを練ることが、成功するホームページへの第一歩です。