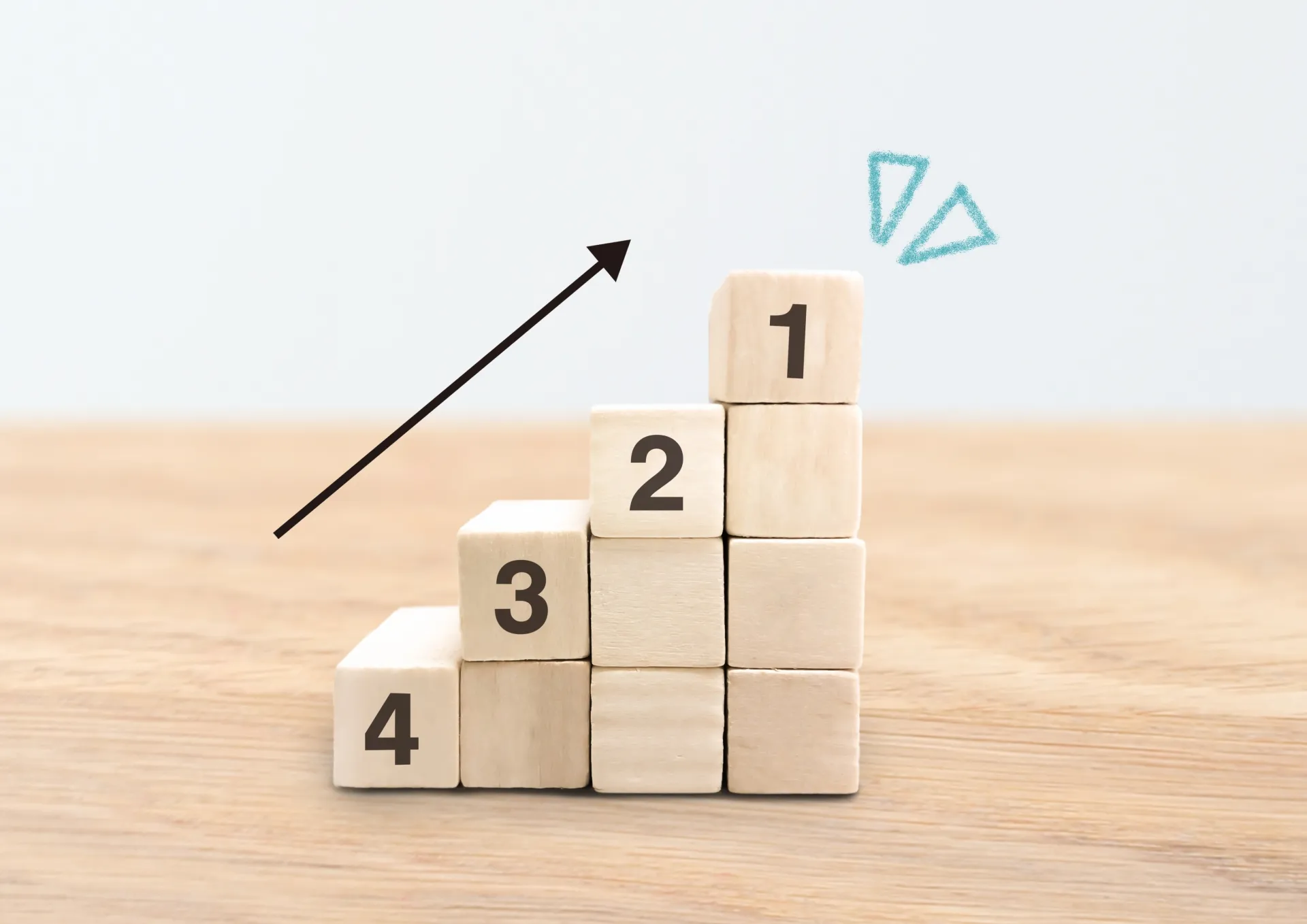「自社のホームページをもっと多くの人に見てもらいたい」「検索結果の上位に表示させたいけれど、何から手をつけて良いか分からない」
企業のホームページ担当者様であれば、このようなお悩みを抱えている方も少なくないのではないでしょうか。特に、SEO対策と聞くと専門知識が必要で難しいと感じ、費用のかかる外部委託を検討されるケースも多いかもしれません。
しかし、ご安心ください。適切な知識と手順を踏めば、自社でホームページのSEO対策を行うことは十分に可能です。本記事では、コーポレートサイトの集客力向上を目指す企業担当者様に向けて、SEO対策の基本的な考え方から具体的な施策まで、ご自身で実践できる方法を分かりやすく解説していきます。専門的な知識がなくても、自社サイトの潜在能力を最大限に引き出すためのヒントがきっと見つかるはずです。
なぜ今、自社での取り組みが重要なのか
SEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)とは、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、自社サイトが上位に表示されるように最適化する一連の施策を指します。検索結果の上位に表示されることで、より多くのユーザーが自社サイトを訪れる可能性が高まり、結果として問い合わせ増加や売上向上に繋がることが期待できます。
かつては小手先のテクニックで検索順位を操作できた時代もありましたが、現在の検索エンジンは、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供しているサイトを高く評価する傾向にあります。そのため、小手先の対策ではなく、ユーザーファーストな視点に基づいたコンテンツ作成とサイト構造の最適化がSEO対策の核となります。
では、なぜ今、自社でSEO対策に取り組むことが重要なのでしょうか。
- 継続的な集客効果: 広告のような一時的な費用ではなく、一度最適化すれば長期的に安定したアクセスが見込めます。
- ブランディング効果: 検索上位に表示されることで、企業の信頼性や専門性が高まり、ブランドイメージの向上に寄与します。
- コスト効率の高さ: 外部に依頼する費用を削減し、自社の人材でノウハウを蓄積しながら対策を進めることができます。
- 市場の変化への対応力: 検索エンジンのアルゴリズムは常に変化します。自社で対策を行うことで、迅速に変化に対応し、柔軟な戦略を立てることが可能になります。
これらの理由から、特にコーポレートサイトを運営する企業にとって、自社でのSEO対策は単なる集客施策に留まらず、企業の成長戦略において不可欠な要素と言えるでしょう。
自社で取り組むSEO対策:実践ロードマップ
それでは、具体的にどのようなステップでSEO対策を進めていけば良いのでしょうか。ここでは、企業担当者様が自社で実践できる具体的な対策をロードマップ形式でご紹介します。
関連記事:ホームページのSEO対策はこれで決まり!基本から学ぶ効果的な方法
ステップ1:キーワード選定の徹底
SEO対策の第一歩は、適切なキーワードを選定することです。どんなに素晴らしいコンテンツを作成しても、ユーザーが検索しないキーワードで最適化されていては意味がありません。
- ターゲットユーザーの明確化:
まず、自社のホームページにどのようなユーザーを呼び込みたいのかを明確にします。彼らはどのような課題を抱え、どのような情報を求めているのでしょうか。 - キーワード候補の洗い出し:
- 自社サービス・製品に関連するキーワード: 自社の事業内容や提供するサービス・製品から連想されるキーワードを列挙します。
- 競合サイトの調査: 競合他社がどのようなキーワードで集客しているかを分析します。
- 顧客の声を活用: 営業担当者やカスタマーサポート部門にヒアリングし、顧客がどのような言葉で自社やサービスについて話すか、どんな疑問を抱いているかを確認します。
- サジェストキーワードの活用: Google検索窓にキーワードを入力した際に表示される「サジェスト機能」や、検索結果ページ下部に表示される「関連性の高い検索」などを参考にします。
- キーワードツールの活用:
- Googleキーワードプランナー: Google広告のアカウントがあれば無料で利用でき、キーワードの月間検索ボリュームや競合性を調査できます。
- ラッコキーワード: 関連キーワードやサジェストキーワードを効率的に洗い出すのに役立ちます。
- Ubersuggest(ウーバーサジェスト): 競合分析やキーワード候補の抽出に活用できます。
- キーワードの優先順位付けと選定:
洗い出したキーワードの中から、以下の要素を考慮して優先順位をつけ、最終的なターゲットキーワードを選定します。- 検索ボリューム: ある程度の検索ボリュームがあるか。少なすぎるとアクセスが見込めず、多すぎると競合が激しく上位表示が難しい場合があります。
- 競合性: 検索結果の上位に表示されているサイトの質や量を確認し、自社が上位表示できる可能性があるかを見極めます。
- 検索意図との合致: そのキーワードで検索するユーザーが、自社サイトに求めている情報と合致するか。例えば、「Webサイト制作 費用」で検索するユーザーは費用の相場を知りたいはずであり、制作事例ばかりでは検索意図に沿っていません。
ポイント: 複数のキーワードを組み合わせた「ロングテールキーワード」(例:「ホームページ 制作 費用 相場 東京」)は、検索ボリュームは少ないものの、検索意図が明確で競合が比較的少ないため、上位表示しやすくコンバージョンに繋がりやすい傾向があります。初期段階ではロングテールキーワードを積極的に狙うことをお勧めします。
ステップ2:良質なコンテンツの作成と最適化(オンページSEO)
キーワード選定が完了したら、そのキーワードで検索するユーザーのニーズを満たす良質なコンテンツを作成し、適切に最適化します。これが「オンページSEO」と呼ばれる施策の核です。
- ユーザーの検索意図を深く理解する:
選定したキーワードで実際にGoogle検索を行い、上位表示されている記事を複数確認します。どのような情報が求められているのか、どのような構成で書かれているのかを分析し、自社コンテンツに活かします。ユーザーが「何を知りたがっているのか」「何を解決したいのか」を徹底的に深掘りすることが重要です。 - 網羅性と専門性の高いコンテンツ:
選定したキーワードに関する情報を網羅的に、かつ専門的な視点から深掘りして提供します。- 独自性の追求: 他のサイトにはない、自社独自の視点やノウハウ、事例などを盛り込むことで、差別化を図ります。
- 一次情報の提供: 自社で行った調査結果や実験データ、顧客へのインタビューなど、一次情報を提供することでコンテンツの信頼性と価値を高めます。
- 具体的な解決策の提示: ユーザーの課題に対する具体的な解決策や、実践的なアドバイスを提供します。
- 読みやすいコンテンツ構造:
- 魅力的なタイトル: ユーザーの興味を引き、クリックしたくなるようなタイトルを作成します。キーワードを自然に含めることを意識します。
- 見出しの活用(hタグ): 記事の構成を分かりやすくするため、h2、h3などの見出しタグを適切に使用します。見出しにもキーワードを含めると効果的です。
- 箇条書きや表の活用: 情報を整理し、視覚的に分かりやすく伝えます。
- 適切な改行と段落分け: 長文にならないよう適度に改行し、段落を分けることで読みやすさを向上させます。
- 画像・動画の活用: 視覚的な情報を提供することで、理解を深め、読者の滞在時間を延ばす効果があります。
- キーワードの自然な配置:
選定したキーワードを、タイトル、見出し、本文中に不自然にならない範囲で自然に含めます。過度なキーワードの詰め込み(キーワードスタッフィング)は、検索エンジンからペナルティを受ける可能性があるため避けてください。 - メタディスクリプションの最適化:
メタディスクリプションは、検索結果に表示されるサイトの説明文です。ユーザーがクリックするかどうかを判断する重要な要素となるため、キーワードを含めつつ、サイトの内容を簡潔かつ魅力的に説明する文を作成します。文字数制限(PCで120字程度、スマホで50~60字程度)を意識しましょう。 - URLの最適化:
URLは短く、内容を示す簡潔なものにし、キーワードを英数字で含めることが推奨されます。日本語URLはエンコードされて長くなるため、推奨されません。
例:https://example.com/seo-strategy/
ステップ3:技術的SEOの実施
コンテンツの質を高めるだけでなく、検索エンジンがサイトを正しく認識し、評価するための技術的な対策も重要です。
- 表示速度の改善:
サイトの表示速度は、ユーザー体験だけでなく、検索順位にも影響を与えます。表示速度が遅いと、ユーザーは離脱しやすくなり、検索エンジンの評価も下がります。- 画像ファイルの最適化: 画像の圧縮や適切なフォーマット(WebPなど)への変換を行います。
- サーバーの応答速度の確認: 利用しているサーバーの性能を確認し、必要に応じてアップグレードを検討します。
- キャッシュの活用: ブラウザキャッシュやサーバーキャッシュを活用し、再訪問時の表示速度を向上させます。
- Google PageSpeed Insights: このツールで自社サイトの表示速度を計測し、改善点を把握しましょう。
- モバイルフレンドリー対応:
スマートフォンの普及により、モバイル端末からのアクセスが主流となっています。Googleもモバイルフレンドリーなサイトを高く評価するため、レスポンシブデザインなどでモバイル対応を行うことは必須です。- Google Search Consoleの「モバイルユーザビリティ」レポート: ここでモバイルフレンドリーに関する問題がないかを確認できます。
- サイト構造の最適化と内部リンクの構築:
- 階層構造の整理: ユーザーや検索エンジンがサイト内を巡回しやすいよう、論理的で分かりやすい階層構造を構築します。
- 内部リンクの設置: 関連性の高い記事やページ同士を内部リンクで繋ぎます。これにより、サイト全体の回遊性が高まり、重要なページに検索エンジンの評価(リンクジュース)が伝わりやすくなります。アンカーテキスト(リンクに設定するテキスト)には、リンク先のキーワードを含めることを意識しましょう。
- パンくずリストの設置: ユーザーがサイト内のどこにいるかを把握しやすくするため、パンくずリストを設置します。
- XMLサイトマップの作成と送信:
XMLサイトマップは、サイト内の全てのページを検索エンジンに伝えるためのファイルです。これをGoogle Search Consoleを通じて送信することで、検索エンジンがサイト内のコンテンツを効率的に発見し、インデックスすることを助けます。 - SSL化(HTTPS化):
サイト全体をSSL化し、通信を暗号化することは、セキュリティの観点だけでなく、SEOにおいても重要です。GoogleはSSL化されたサイトを優先的に評価する傾向があります。まだ未対応の場合は速やかに実施しましょう。 - Google Search Consoleへの登録:
Google Search Consoleは、Googleが自社サイトをどのように認識しているか、どのような問題が発生しているかを確認できる無料ツールです。検索パフォーマンス、カバレッジ、モバイルユーザビリティ、コアウェブバイタルなどのレポートを定期的に確認し、サイトの状態を把握しましょう。
ステップ4:成果測定と改善(PDCAサイクル)
SEO対策は一度行ったら終わりではありません。継続的な改善が成功の鍵です。
- 効果測定ツールの導入:
- Google Search Console: 検索パフォーマンス(表示回数、クリック数、CTR、検索順位)を把握します。
- Google Analytics 4(GA4): アクセス数、ユーザーの行動(滞在時間、回遊率、コンバージョン)などを詳細に分析します。
- 現状分析と課題特定:
ツールのデータをもとに、以下の点を分析します。- どのキーワードでアクセスを集めているか。
- 目標とするキーワードで上位表示できているか。
- ユーザーはどのページをよく見ているか、どこで離脱しているか。
- コンバージョンに繋がっているか。
- 改善策の立案と実行:
分析結果に基づいて、改善策を立案し実行します。- 順位が低いキーワードのコンテンツをリライト・加筆修正する。
- 表示速度の遅いページを改善する。
- 離脱率の高いページのコンテンツやデザインを見直す。
- 競合サイトの新しい動向をチェックし、自社サイトに取り入れる。
- PDCAサイクルを回す:
Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)のサイクルを継続的に回すことで、SEO効果を最大化していきます。
やってはいけないことと最新トレンド
自社でSEO対策を進める上で、特に注意すべき点と、近年のトレンドについても触れておきます。
避けるべきSEO対策(ブラックハットSEO)
かつて効果があったとされる手法の中には、現在では検索エンジンからペナルティを受ける「ブラックハットSEO」と呼ばれるものがあります。これらの手法は絶対に避けるべきです。
- キーワードの過剰な詰め込み(キーワードスタッフィング): 不自然なほどキーワードを羅列する行為。
- 隠しテキストや隠しリンク: ユーザーには見えないようにキーワードやリンクを埋め込む行為。
- コンテンツの複製(コピーコンテンツ): 他サイトの記事をそのままコピーしたり、少し変更しただけで公開する行為。
- 質の低い被リンクの大量獲得: 関連性の低いサイトからのリンクを大量に購入したり、自動生成ツールで獲得する行為。
これらの手法は短期的に効果があるように見えても、最終的には検索順位の低下やインデックス削除といった重いペナルティに繋がるため、絶対に手を出さないでください。
最新のSEOトレンドと対応
検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しています。主要なトレンドを把握し、自社サイトに反映させることが重要です。
- E-A-T(専門性・権威性・信頼性)の重要性: 特にYMYL(Your Money or Your Life:人々の幸福、健康、経済的安定、安全に影響を与える可能性のある分野)コンテンツにおいては、誰が、どのような専門性を持って執筆しているかが重視されます。執筆者のプロフィールを明記したり、公的な情報源を引用するなど、サイト全体のE-A-Tを高める努力が必要です。
- Core Web Vitals(コアウェブバイタル): Googleがユーザー体験を測る指標として導入したもので、ページの読み込み速度(LCP)、インタラクティブ性(FID)、視覚的な安定性(CLS)の3つの指標で構成されます。これらの指標を改善することは、SEOに直結します。
- 自然言語処理の進化: 検索エンジンは、キーワードだけでなく、文脈やユーザーの意図をより深く理解するようになっています。そのため、ユーザーの疑問を包括的に解決する「トピック網羅型」のコンテンツが評価されやすくなっています。
- AIコンテンツの活用と注意点: ChatGPTなどの生成AIツールを活用してコンテンツを作成する企業も増えていますが、AIが生成しただけの情報をそのまま公開することは推奨されません。必ず人間の手でファクトチェック、情報の加筆修正、独自性の付与を行うことで、ユーザーにとって価値のあるコンテンツに仕上げる必要があります。あくまで作成補助ツールとして活用し、E-A-Tの観点から人間が監修することが不可欠です。
継続的な努力がホームページを成長させる
本記事では、ホームページのSEO対策を自社で行うための具体的な方法を解説しました。キーワード選定からコンテンツ作成、技術的最適化、そして効果測定と改善のPDCAサイクルまで、多岐にわたる施策がありますが、これらは決して特別な知識がなければできないことではありません。
重要なのは、
- ユーザーファーストの視点: 常にユーザーが何を求めているのかを考え、それに応えるコンテンツとサイト体験を提供すること。
- 継続的な努力: SEO対策は一朝一夕で結果が出るものではなく、地道な改善と長期的な視点が必要です。
自社のホームページを「企業の顔」として成長させ、より多くの見込み客との接点を創出するためにも、今回ご紹介した内容を参考に、ぜひ自社でのSEO対策に取り組んでみてください。不明点や疑問点は、Google Search ConsoleやGoogle Analytics 4のヘルプ、信頼できるSEO情報を発信しているブログなどで調べながら、一歩ずつ進めていくことが成功への近道です。